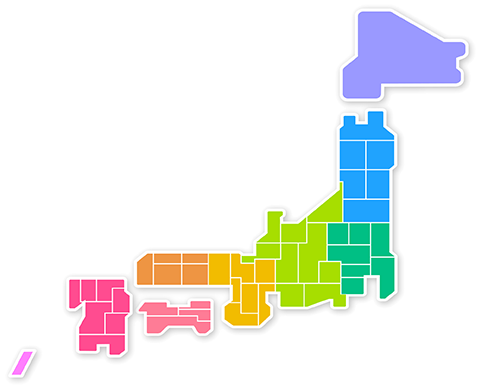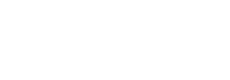「医療機器の製造販売を始めるにはどのような申請や許可が必要なのか、気になる人もいるのではないでしょうか。医療機器は人体に与える影響が大きいため、ユーザー側としても信頼できる業者に取り扱ってほしいものですよね。
日本は、国内で医療機器を製造販売できるようになるまでに様々な規制や認証、審査などが設けられています。
今回の記事では、その中から「医療機器認証」をテーマに解説します。医療機器の中でも、特にクラスⅡ、クラスⅢに関係しています。ぜひ参考にして下さいね。
「医療機器認証」とは?
「医療機器認証」について、制度や申請にかかる日数・費用などを解説します。
医療機器の登録認証機関制度とは
高度管理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下、指定高度管理医療機器等という)を製造販売する際には、登録認証機関から認証(第三者認証)を受ける必要があります。
指定高度管理医療機器等とは、厚生労働大臣によって認証基準を定められている医療機器のことです。これらの医療機器を製造販売するためには、品目ごとに登録認証機関からの認証を受ける必要があります。
例えば、家庭用マッサージ器や補聴器など、一つ一つに対して認証が必要です。
指定高度管理医療機器等には共通した認証基準があるので、厚生労働省に登録された機関でも認証が可能です。
認証基準のない医療機器の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による承認審査と、厚生労働大臣の承認が必要となります。
医療機器認証と「クラス」
医療機器のクラスは、「万が一機器に不具合が起きた場合の、人体に生じるリスクの大きさ」によって分けられています。
国際分類(薬事法分類):リスクの定義
クラスⅠ(一般医療機器):人体へのリスクが極めて低い。
クラスⅡ(管理医療機器):人体へのリスクが比較的低い。
クラスⅢ(高度管理医療機器):人体へのリスクが比較的高い。
クラスⅣ(高度管理医療機器):生命の危険に直結する危険がある。
医療機器認証の対象となるのはクラスⅡ~Ⅲの医療機器のうち、厚生労働大臣から指定されているものです。
クラスⅡ~Ⅲの医療機器
クラスⅡ~Ⅲの医療機器について、それぞれ解説します。
〈クラスⅡ〉
クラスⅡは、大半の医療機器が第三者認証です。
【指定管理医療機器】
・認証基準があるもの→登録認証機関による第三者認証
・認証基準がないもの→PMDAによる承認審査
【管理医療機器】
PMDAによる承認審査
〈クラスⅢ〉
クラスⅢは、一部を第三者認証で行い、それ以外はすべてPMDAによる承認審査です。
【指定高度管理医療機器】
登録認証機関による第三者認証
【高度管理医療機器】
PMDAによる承認審査
医療機器認証の具体的な品目は?
医療機器認証の対象となる医療機器は数が多いので、ここでは比較的なじみのある品目を中心に紹介します。
【管理医療機器】
・歯科用機器
・家庭用マッサージ器、家庭用電気治療器及びその関連機器
・補聴器
・麻酔、呼吸用機器
【高度管理医療機器】
・インスリンペン型注入器
・経腸栄養用輸液ポンプ、汎用輸液ポンプ、注射筒輸液ポンプ、患者管理無痛法用輸液ポンプ
・不整脈モニタリングシステム、無呼吸モニタ、無呼吸アラーム、心電・呼吸モジュール
参考:認証範囲一覧(厚生労働省)
認証にかかる日数と費用の目安は?
登録認証機関による第三者認証にかかる日数と費用は、下記の通りです。
【日数】
書類等の準備期間:約4~6ヶ月
申請から認証まで:約2~3ヶ月
【費用】
認証手数料:約50万~100万円/1製品(個別交渉が可能)
コンサルティングに依頼した場合:約60万~100万円
それ以外にも、あらかじめ「QMS適合性調査」に合格しておく必要があります。
「医療機器認証」の注意点と申請方法

「医療機器認証」の注意点と、申請方法について解説します。
【1】登録認証機関ごとに認証できる品目が異なる
指定高度管理医療機器等は、登録認証機関ごとに認証できる「品目」が異なります。一ヶ所でほとんどの品目を網羅しているところもあれば、複数品目のみというところもあります。
また、登録認証機関が認証業務を廃止している場合もあるので、注意が必要です。
「認証範囲一覧」は厚生労働省のホームページでも確認できますが、最新情報については直接登録認証機関に問い合わせることをおすすめします。
参考:認証範囲一覧(厚生労働省)
【2】医療機器認証の申請方法
申請者:医療機器製造販売業許可業者
申請先:厚生労働省に登録されている登録認証機関
添付書類:
(1)認証申請書
・類別
・名称
・使用目的、効能、効果
・形状、構造および原理
・原材料または構成部品
など
(2)添付資料
製品の品質や性能、安全性などが、国の定める認証基準を満たしていると立証できる資料が必要です。製品によって異なります。
まとめ:医療機器認証は下調べや書類準備にも時間をかけて
医療機器認証はすべての医療機器に必要があるわけではなく、クラスⅡ・Ⅲの医療機器のみが対象です。
認証を受けられる品目は、登録認証機関によって異なります。品目をピックアップしたら、必ず登録認証機関に問い合わせてみましょう。
医療機器認証には、日数や費用がかなり必要です。
申請書類の準備には約半年、申請から認証までにはさらに半年ほど必要です。費用も、認証手数料が1製品につき約50万~100万円かかります。
ですが、せっかく手間をかけても、認証基準を満たしていないと判断された場合は認証を受けられません。
専門的な書類も多く必要になるので、コンサルタントに相談しながら進めるのもおすすめです。
ボンドジャパンでは、超音波診断装置、内視鏡をはじめ、 CT、MRI、レントゲンなどの医療関連機器から、整骨院向け機器まであらゆる中古医療機器の販売・買取を行っております。ぜひご相談ください。
中古医療機器を買いたい方はこちら
中古医療機器を売りたい方はこちら
関連記事
医療機器の製造販売に必須の「医療機器製造販売業」できることや申請方法を解説
超音波診断装置とは?装置のしくみや検査でわかることを解説